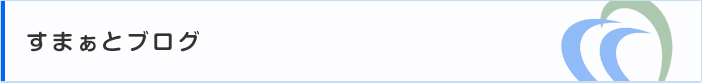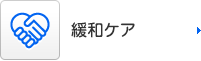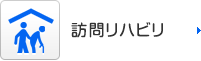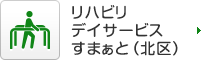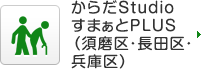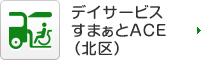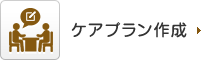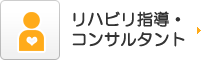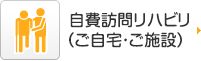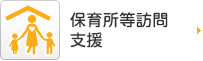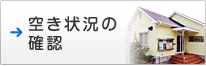「私達の中にあるもの」
ここでは、スタッフの思いを綴っていきます。
私達は自分の中にあるものしか投影できないのです。共感したいなら自分の中の感受性を高めなければなりません。 美しいもの、喜び、悲しみ、感動、笑顔、涙。受け取る事のできる感性を磨いていきたい。
体操教室に参加させていただきました
2021年01月14日


1月14日に「健康になろう会」の体操教室に、からだStudioすまぁとPLUSが参加させていただきました。この会は、名倉あんしんすこやかセンター様が地域のご高齢の皆様へ向けて定期的に開催している健康イベントです。
今回、お招きいただきまして、開催場所のコープ長田店にて体操教室の講師を理学療法士藤原が務めさせていただきました。
体操教室では、椅子に座った状態でできるストレッチや筋肉トレーニング、二重課題など、介護予防に役立つ体操をご参加者と共に1時間ほど行わせていただきました。
二重課題では、笑い声が絶えず盛り上がり、最後の体操では洋楽のバックミュージックの中、スポーツジム感覚で汗を流されました。ご参加者の皆様には、ご自宅でもご自身やご家族の方々とも行えるように、当日行った体操プログラムをお配りしました。
毎日、少しでもお身体を動かしてていただき、皆様のご健康にお役立ていただけたらと思います。
今後も引き続き、地域の皆様の健康にお役に立てるような活動を積極的に行いつつ、運動を通して「からだとこころのバランス」をよい状態に保てるように努力して参ります。
ご参加様の皆様、お招きいただきました「名倉あんしんすこやかセンター」の皆様、ありがとうございました。
からだStudioすまぁとPLUS 内覧会のご報告
2020年04月28日

新規デイサービスの内覧会実施中です
コロナウイルス感染拡大防止により少人数、完全予約制となっております。
予約時間を十分間隔をあけ密集を避け、室内換気、消毒など徹底した管理のもと開催させて頂いております。
開催中内覧会ではご利用者様、ケアマネージャー様をはじめ各関係者の方々に内覧会へ足を運んでいただいており「今までにないタイプのデイサービス」、「次世代型な流れ」、「運動がたくさんできそうですね」と嬉しいお言葉を頂戴しております。
からだStudioすまぁとPLUS ★2020.5 OPEN★
利用者様も募集しております(^^)/
ご興味がある方は是非一度見学にお越しください。
また、オンライン内覧会も同時開催中です。
お気軽にお問合せ下さいませ。
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
腰痛予防とピラティス
2018年08月17日

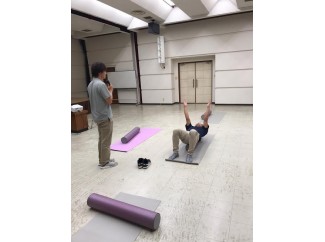
平成30年8月16日に、「ピラティスによる腰痛予防アプローチの紹介」というテーマで医療・介護関係の方を対象にお話をさせていただく機会をいただきました。
腰痛に対して理解を深めるとともに、実技を通して姿勢のニュートラルを感じていただきました。
「いつまでも自分のやりたいことができる」ようにリハビリ×ピラティスを通して心と身体をメンテナンスしていきましょう。
勉強会
2018年02月06日


しあわせの村の会議室にて、イングレンタルサービス様をお招きし、最新の福祉用具の取り扱いについて勉強会を開催しました。
その他にも薬に関する勉強会や、脱水・感染予防対策・事例検討会等、スタッフの知識や技術向上のための勉強会を定期的に行っていますので、またご紹介できればと思います。
2016年 忘年会
2016年12月09日

先日、忘年会をいたしました。すまぁとのステーション3拠点、デイサービス、連携している医院、薬局も一緒に中華料理を楽しみました。今年もいよいよ暮れが迫ってまいりました。みなさま、大変お疲れ様でした。